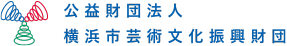コラム COLUMN
夏草や・・・
麦畑(むぎばた)の 陽(ひ)に意味なき死 和を求む
A sunny wheat field
Strewn with senseless death
Hungry for peace
元ベルギー首相で、EU初代大統領を務めたヘルマン・ファンロンパイ氏が、2022年7月の来日中に、ロシアの進攻に苦しむウクライナへの想いを俳句に呼んだものです。同氏は、自作の俳句集(母国語であるフラマン語に加え、英独仏などに翻訳されている)を2冊も出しているほどの有名な俳句愛好家なのです。
麦畑はウクライナの象徴で黄色で表され、空の青と共に国旗になっています。ファンロンパイ氏は美しい麦畑に、いまや多数の兵士や民間人の非業の死が折り重なっているであろうことに、強い悲しみと憤りを感じているのでしょう。最後のhungry は、世界有数の小麦生産国ウクライナから小麦が輸出されなくなったことにより、アフリカなど貧しい国々の小麦の不足が「飢饉」を招くのではないかという懸念と、平和への「渇望」とをかけています。日本人が好んで使う「掛詞」を英語においてもうまく使っているのです。
友人の紹介で、都内のあるゲストハウスで同夫妻と夕食を共にする機会がありました。氏は、俳句は今や日本を出て、世界のHAIKU になった。外国語による俳句でも、5-7-5の音節や、季語の約束事は守っている。17文字という短さとこれらのルールは、言いたいことを十分表せない制約になると思うかも知れない。しかしそもそも俳句とは自らの心情を切々と訴えるものではなく、身の回りの些細な出来事に注意を払い、それをさらりと詠むことで他者の連想と共感を呼び起こすものだ。いわば自己中心でなく、他者を中心においた文学といえる。だからかえって長編の詩よりも素人にはとっつき易く、子供でも見事な俳句を詠めるということを紹介してくれました。
誰もが目の前の権力や富に振り回され、自我の虜になっているように見える今日でも、他者との調和を重んじる人間本来の精神がまだ残っており、俳句はそれを取り戻させる機会になると述べられました。
日本語独特のニュアンスや四季を表す季節感は、外国語の俳句では表現し難いのではないかとお尋ねすると、どの国にもユニークで国民に親しまれている文化や気候があるので、短い言葉でそれを連想させることができる俳句の表現形式は大変魅力的だ。それが俳句の人気の秘訣なので、日本発だからと言って、日本の四季が表現できなければならないということではないと明確なお答えが返ってきました。
私から、ファンロンパイ氏が詠んだウクライナの句(麦畑・・・)は、芭蕉が「奥の細道」の旅の途次、奥州藤原氏が栄華を夢見た平泉(岩手県)ではかなく散った兵士たちを憐れんで詠んだ
夏草や 兵(つわもの)どもが 夢の跡
や、
後半に加賀の国(石川県)の太田神社で斎藤実盛を憐れんで詠んだ
むざんやな 甲(かぶと)の下の きりぎりす
に通じるところがあると言ったところ、うれしそうにメモをとっていました。猛き武将の悲劇と小さな無垢の虫の対比がいいと言われました。
そして話題はその芭蕉が出羽の国(山形県)で詠んだ、
閑かさや 岩にしみいる 蝉の声
に移りました。夏の暑さの中に、人生の無常を感じさせるものです。
* * *
そこでふと気づいたのです。ゲストハウスの庭やその周辺からは蝉の声が聞こえてこないのです。今年は蝉たちはどこへ行ってしまったのでしょうか。前号でレイチェル・カーソンの『沈黙の春』について書きましたが、いまや『沈黙の夏』なのでしょうか。季節が巡ってくるたびに、懐かしい音が一つひとつ無くなっていくのは止められないのでしょうか。
公益財団法人横浜市芸術文化振興財団
理事長 近藤誠一