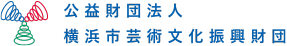コラム COLUMN
第3回 専門人材育成研修【舞台芸術系】
現場の実感に基づく意見交換。切磋琢磨で専門性を高める
昨年12月17日、舞台芸術系プロデューサーを育成する研修が、横浜みなとみらいホールレセプションルームで実施された。対象は、横浜市芸術文化振興財団が運営する舞台芸術系の専門施設等の職員。令和2年度は13人が参加した。
プロデューサーに求められる能力は多岐にわたる。滞りなく公演を実施する実務能力も必要だし、市民(観客)のニーズをつかむ洞察力も求められる。効果的なプロモーションも考えなければならない。
さまざまな課題の中から、今年度は「『公共性』および『発信性』とは何か」をテーマにした。どちらも企画立案に深く関わり、また人によってとらえ方が異なる概念でもある。
活発な意見交換が行われたが、その前に、研修全体を概観しておきたい。
初日は6月。元テレビ朝日プロデューサーで、「題名のない音楽会」などの音楽番組を手がけた大石泰さんを講師に招いて、講義が行われた。
次に、10月に横浜みなとみらいホールで開催された「発達障がい支援ワークショップIN横浜 音と光の動物園」を鑑賞。大石さんから「ワークショップの感想と、『個人のニーズに寄り添うことと公共性は両立するか』というテーマで考察を書いてください」という課題が出された。
3回目の最終日が、12月17日の横浜みなとみらいホールである。ここではレポートの講評とディスカッションを行う。半年かけて、テーマについての考察を深めるプログラムになっている。
講評を終えて午後3時すぎ。「これまでの演習を鑑みて、財団における公共性・発信性について、みなさんの考えをお話しください」。横浜みなとみらいホールの佐々木真二チーフプロデューサーの呼びかけでディスカッションが始まった。
横浜能楽堂で古典芸能プロデューサーを務める秦野五花さんは、障がいのある人も健常者も一緒に楽しめる「バリアフリー能」の企画をしている。「個人のニーズと公共性」は身近なテーマだ。「むしろ、社会の中で置き去りになりがちな人に光をあて、手助けすることこそ公共の役割ではないか」とする。
同じく横浜能楽堂の遠山香織さんも、「公共性についてはすごく考える」という。障がいのある人に直接ヒアリングする機会も多い。だからこそ、「無数にある個別のニーズにすべて応えることはできない」と感じる。財団が複数の専門施設を運営することに注目し、「さまざまな専門性を持つ複数の活動主体が連携することで、受け皿を増やせるのではないか」とアイデアを出した。
横浜みなとみらいホールの飯島玲名さんは、「財団における『公共』は、『誰に対しても開かれている』という意味合いが強いと考えた」という。「現在実施している事業は(個人のニーズよりも)広く関心を集めることが主で、障がい者の参加が難しい場合もある。少数者に寄り添うことも公共施設の役割の一つであり、これからの課題」と述べた。
一方、横浜にぎわい座の田谷祐紀さんは、「落語講談浪曲といった寄席演芸にはもともと、一般的なものとは真逆のニヒリズムや(社会への)批判的な視点がある」という。「コアなファンはそこを楽しむが、メディアの発達で寄席演芸も一般性を帯びるようになった。『儲かる興行』は明確にあるが、それだけでは特色が出ない」と話す。
協働推進グループでフェスティバル事業や交流事業に携わる千装功さんは、ワークショップの福祉的な側面を指摘した。「アートの分野でやるならば、別のアプローチがあるのではないか。我々も公益財団法人を名乗っているが、公共サービスとは少し違う。むしろ専門施設であることの意義を突き詰めていって、発信性を伴うことで公共のものにしていく。そんなイメージを持った」と話した。
横浜赤レンガ倉庫1号館でダンスプロデューサーを務める中祖杏奈さんも、「芸術においての公共性」を強調する。「アートには独創性が不可欠。もし『みんなが良いというもの』が公共性の意味するところであれば、新しい何かを創り出すことができなくなる」ととらえる。
協働推進グループの阿部晃久さんは、「大石先生が『需要は生み出すもの』とはっきりおっしゃったのが心強い。私たちはそれぞれ専門分野が異なるが、根幹には(舞台芸術への)『感動』があって、それを人につなげていきたいという思いがある。そこを信じていいんだと思えた」と話した。
他にもさまざまな意見があった。すべての発言に触れることはできないが、現場の実感に基づく言葉は説得力があり、真摯な意見交換が行われた。
続いて各施設のチーフプロデューサーや支配人が発言した。目立ったのは「発信性」への言及だ。
「イベントに参加していない人たちにどう伝えるかということこそが、こういうごく一部の人に対して実施していくワークショップの価値を生み出すことではないか。その意味で、発信性とどう結びつけられるかが、実はすごく重要」(横浜みなとみらいホール・菊地健一チーフプロデューサー)
「発信性を持って初めて、公共のものになると、強く思う。公共性と発信性がうまく連鎖している例として、『こども食堂』をイメージした。劇場に来ない人も含めて、どう広げていくかを考えなければいけない」(横浜能楽堂・菅原幸子支配人)
「公共性のある企画」があるのではなく、外へ発信することで、企画が公共性を獲得していく。こういった視点の持ち方にこそ、プロデューサーとしての専門性が現れると言っていい。
午後4時すぎ。最後に、横浜赤レンガ倉庫1号館の小野晋司館長のモデレートで、次年度のテーマを話し合った。まず、それぞれの現状を報告しながら、今抱えている課題を出し合う。コロナ禍を反映して、「公演の中止が相次いだ」「海外からの招聘を断念した」などの悩みが共有された。一方、オンラインの取り組みの報告も相次いだ。
横浜みなとみらいホールは「横浜WEBステージ」を企画・制作。楽器の中にカメラを仕込むなど、動画配信ならではの工夫を凝らした。制作に携わった飯島さんは「劇場に来られなくても、新しい音楽の楽しみ方を発信できることを学んだ」という。
横浜にぎわい座は、「寄席控え」をする高齢のお客様も多く、現状は厳しい。一方で演者の側には「ものすごい意識改革が起こった」と田谷さんはいう。客前を大事にする寄席演芸で、YouTube中継にトライする落語家が現れた。「(劇場再開後の)寄席の客足はむしろ伸びている。ライブとオンラインの共存は可能だと、今のところは感じている」
現在は、制限付きとはいえ、劇場は開いている。しかし、「この状況下で人を集めること自体がどうなのか」という根本的な不安はぬぐい難い。舞台芸術の意義を問われ続けた1年。小野さんは、「今は自分たちの取り組みを見直すチャンス。その方向で次年度のテーマを設定しましょう」と言って、話し合いを締めた。
小野さんは「自分たちの課題を自分たちで見つけていくことが、この制度の立脚点」と語る。研修で得たものを現場に持ち帰り、現場の課題を次の研修で持ち寄る。そんなサイクルが生まれつつある。
文:長瀬千雅(ライター)