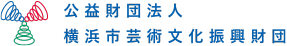コラム COLUMN
鴫立沢
心なき 身にもあはれはしられけり しぎたつさはの秋の夕暮
これはこのコラムで2度ほど引用した、藤原定家の「秋きぬと・・・」と共に秋の夕暮れを歌った3つの名歌(「三夕の歌」)のひとつとされているもので、西行法師が神奈川県大磯で歌ったものです(3つ目は寂蓮法師の歌)。
沢辺を歩いているときに、突然鴫(しぎ)が飛び立つ羽音に驚いたという、それだけの歌です。しかしそこにはものの趣など分かる自分ではないという謙虚さと、それでも一瞬の羽音で気づかせてくれる自然の静寂さ、奥の深さにしみじみとした情緒を感じたという、日本人が古来大切にしてきた心情がたった31文字で見事に表されています。
日本人は自然を自分と同じ仲間として敬い、愛し、いたわるという精神を継承してきました。これに対し近代文明を創り、世界に広めてきた西洋は、中世のころから自然は人間とは異なる存在だとして客体視するようになりました。それはキリスト教の教えの広がりに関係しているようです。神はまず天と地(自然)を創り、そして人間を創られて「地を従わせよ」と言われたからです(『聖書』創世記第一章)。
人間という主体は、自分とは異なるものとして神が創られた自然という客体の仕組みを知るために、外から「観察」し、仮説を立て、実験を通してそれを確認するという過程を経て知識を拡げてきました。その結果できたのが自然科学という学問です。誰がどのような状況で実験を行っても同じ結果が出るならば、それは「客観的真実」だということです。そしてこれはやがて宗教の世界から離れてのちのデカルト(17世紀フランスの哲学者)などがとった「主客二元論」(人間を主体、自然(環境)を機械のような客体と分ける考え方)という西欧文明の根幹となる知的枠組みへと発達しました。
人類はこの知的体系によって宇宙の物理法則を発見し、それを利用してテクノロジーを発達させ、その力によって産業革命や情報革命を達成し、更に資本主義や民主主義などの近代政治・社会制度をつくってきました。その総体が今日の文明と言われるものです。
しかしその自然を客体と見る思想は、大きな問題を孕んでいます。それは対象である自然を次々と分解してその構成要素が何であるかを分析する(いわゆる要素還元主義)ことはできても、自然の本質である「生命」は理解できないからです。いまの科学は、生命体を構成する最小の単位が遺伝子であることは突き止めましたが、依然として生命の謎は解けません。生命は部品が集まってできた機械ではないのです。
自然は古代ギリシャ語で「ピュシス」と言い、「生まれる」という意味とつらなっており、そこには「おのずから生まれ、成長し、一定の完成度に達すると自ら衰え、滅びてゆく」ものという発想があります。生命をこのように捉え、自然とは人間にとって「内から直観され理解される同質者」(伊東俊太郎『文明と自然』)であるという発想によってこそ、生命の本質に迫ることができるのです。
デカルト的な自然機械論に立つ限り、「生命とは何か」は理解できず、自然の生態系の微妙な摂理の軽視、テクノロジーによる資源収奪、ひいては気候変動などの自然破壊を止めることは期待できません。
しかし文明のあまりの成功(少なくとも表面的には)に思い上がっているゆえに、このことはあまり重視されません。人間は自然と一体で、主と客に分けることはできないという発想は、未開社会の、劣った「非科学的」思想で「いかがわしい」ものだという観念が欧米以外の社会にも根強く広がってしまったからです。
そこで重要なのが、自然と自分を一体と見る日本人の伝統的な感覚です。それは未開の時代からの連続のように見えても、西洋文明を吸収して一時は世界第二の経済大国にまでなった先進国日本の国民が、いまだにその生活や習慣の中にしっかりともっていること(つまり自然科学と矛盾するものとは捉えられていないこと)なのです。このことは、SDGsを始め、現代の人類の最重要課題を解決する上で、世界の模範となる思想です。いま国際的に行われ始めているSDGsや脱炭素の動きは、依然として主体たる人間の都合のよい範囲で問題解決に取り組んでいるという、いわば「アリバイ」づくりの域を出ていません。人間一人一人の自然に対する心構えが変わらぬ限り、その場しのぎの政策で終わってしまうでしょう。
現に各国はウクライナにおける戦闘やそれに端を発する国際経済の揺らぎへの対応策に夢中で、気候変動枠組み条約(COP)下での各国のCO2削減目標の達成は後回しです。
西洋がリードしてきた文明の欠陥を修復し、アリストテレスなど古代ギリシャ人がそうであったような人間として持つべき自然観を取り戻すには、日本人の自然観が重要な役割を果たすでしょう。冒頭の西行の歌のように、日本人の生活習慣、文学、芸術にはそのような精神が深く埋め込まれています。講演で理屈を述べても、自信に満ちた西洋人は聞く耳をもたないでしょう。文化により、世界のひとびとの感性に訴えることによってのみ、それはいつの日にか可能となるのではないでしょうか。
「いつになったら西洋が東洋を了解するであろう、否、了解しようと努めるであろう」
(岡倉天心『茶の本』)
公益財団法人横浜市芸術文化振興財団
理事長 近藤誠一