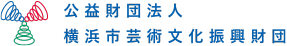コラム COLUMN
夜桜能
月初め、東京の靖国神社で恒例の薪能である「夜桜能」がありました。
上るころに行われた「火入れ式」です。
舞台の左右両脇にあるかがり火が、松明(たいまつ)によって着火された瞬間は、何故かこころがときめきました。それは何故でしょう?人類は古来、燃え盛る炎を恐れながらも、そこに何かを感じてきたはずです。火祭り、火柱など、どの民族にも火を中心においた祭りや行事が沢山あるからです。
私が在勤したデンマークでは、毎年夏至の日に海岸で大きな薪を山積みにし、日没と同時に火をつける習わしがありました。そしてそのてっぺんには柱に縛られた魔女の藁人形が立てられていました。デンマークの友人によると、これは夏至が過ぎると、日増しに日照時間が減り、暗く、寒い冬に向かうので、火のエネルギーを太陽に送ることで、何とか太陽に頑張ってもらおうと祈る気持ちから来たとのことでした。北欧ならではの催事と言えるでしょう。
そこで何故毎年魔女の人形を焼くのか聞いたところ、厄をドイツに送り込むためなのだという答えが返ってきました。近代において幾度となく強力なドイツに攻められ、領土を失ったデンマーク人の民族としての悔しさが、こうしたかたちで明るく表現されるのは、さすが大人の国デンマークだと思いました。
話を薪能に戻しましょう。炎に照らし出された能面の美しさと、それによって深まる陰、そして漆黒の背景に浮かび上がる能衣裳は、この世と別世界の間を行き交う存在のように思えました。闇の中の火は、神と人間の橋渡しをしてくれるという想いが昔からあったのでしょう。その時、目の前をひとひらのサクラの花びらが舞い落ちました・・・。美しい、否、なぜか哀しい、という言葉でしか表せない風情でした。
欧米では美とは力強さや崇高さの象徴です。しかし日本人は美が極まったとき、そこに「哀しさ」を感じるような気がします。天才作曲家モーツアルトの曲を、「悲しみは疾走する、涙は追いつけない」と表現した小林秀雄の「悲しみ」は、万葉以来の「かなし」であり、心を動かす美の究極を表す言葉、というか概念であるような気がします。
それを漆黒の闇と燃え盛る炎と、その前を横切る花びらに感じたのは当然かもしれません。
火を恐れるだけでなく、神との接点として崇めた人類は、やがてエネルギーの源として利用することを覚え、遂に偉大な文明を発展させました。しかしそれは豊かさと利便さの果てしなき追求に使われ、遂に自然の破壊や社会の分断を招くという皮肉な結果となりつつあります。
そのような今だからこそ、古代の素朴な感動を想起させ、人類が自然の一部であったときの姿を呼び起こしてくれる炎に、感動を覚えたのでしょう。